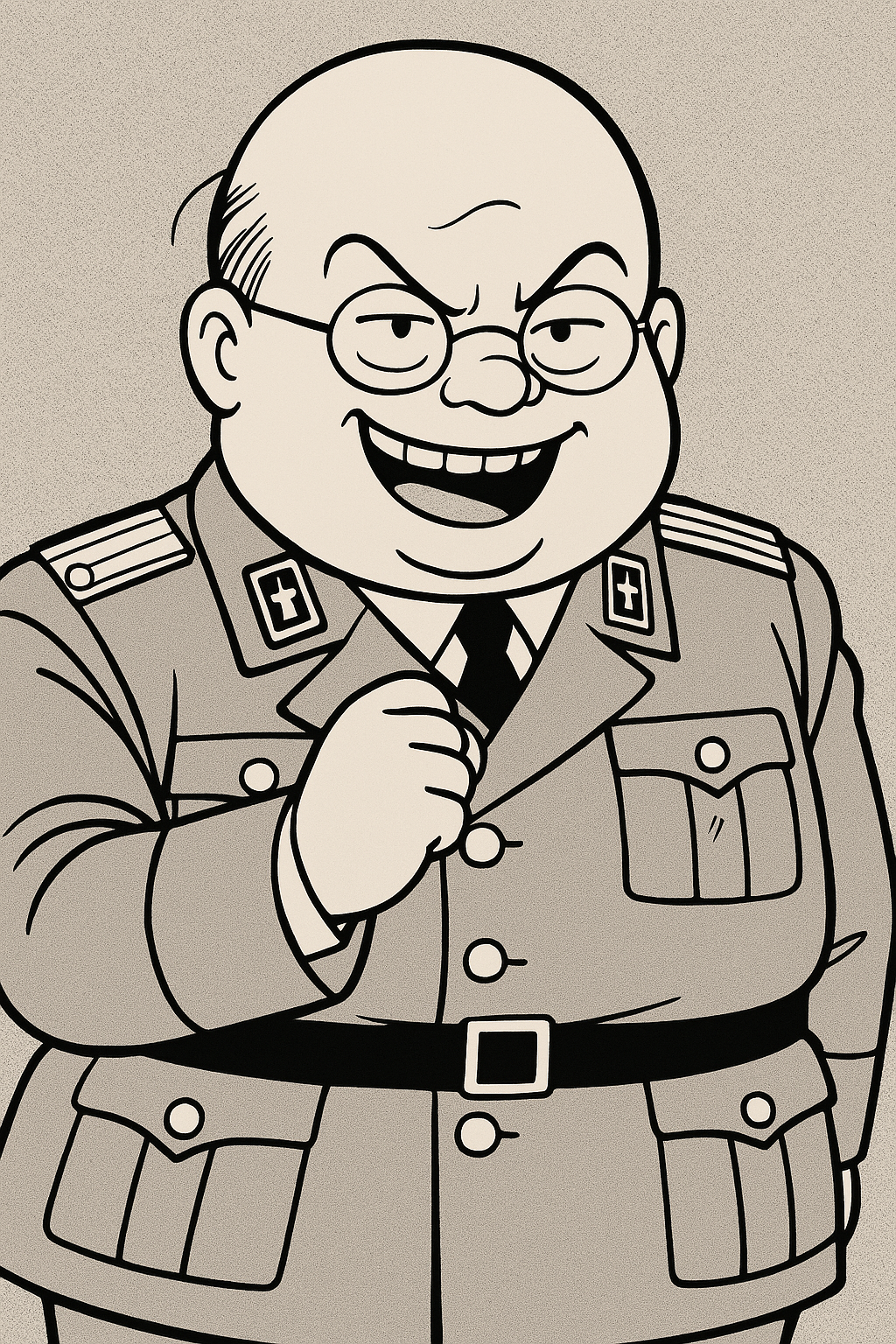2025.03.26 アニメ・特撮ヒーローから鑑みたグリーフのコラム
【鬼滅の刃に学ぶ】“死”を描く物語がなぜ心を打つのか?終末期ケア専門士が読み解く癒しと再生

「人は死んだら、どうなるのか?」
この問いに向き合いながら生きるのが、現代の日本社会です。
そんな中、多くの人の心を動かした作品『鬼滅の刃』。
この記事では、終末期ケア・グリーフケアの専門家の視点から、なぜこの作品がこれほど共感を呼んだのかを読み解きます。
『鬼滅の刃』が現代人に刺さる理由とは?
RPGのような成長物語が生む“自己肯定感”
『鬼滅の刃』の物語構造は、まるでロールプレイングゲーム(RPG)のようです。
- 主人公・炭治郎の成長と修行
- 仲間との絆とパーティーの形成
- 強敵との戦いと乗り越える試練
このような展開は、「現実では報われない」と感じている人々に、努力が認められる物語として受け入れられています。
“死”を丁寧に描くからこそ得られる癒し
鬼たちにも哀しみや過去がある。仲間の死も決して軽んじられない。
そして最終話では、まるで転生したかのような子孫たちが平和に暮らす姿が描かれます。
これこそが、現代人の心をとらえた「死んでも報われる」「生きた証が未来に残る」というメッセージです。
“転生モノ”と現代人の死生観の関係
近年人気の「異世界転生モノ」も、『鬼滅の刃』と同じ文脈で捉えることができます。背景には次のような心理があります。
- 現実の生きづらさや閉塞感
- 人生をやり直したいという願望
- 死後にも続く“物語”への希望
現実では叶わないからこそ、物語の中でだけでも再出発を願う。
その象徴が、転生や再会、未来での幸せな暮らしです。
終末期ケア・グリーフケアの視点から見る“物語の力”
私は終末期ケア専門士・グリーフケア専門士として、命の終わりと向き合う仕事に携わっています。
その中で実感するのは、人は「言葉にできない悲しみ」を物語によって癒やされることがある、ということです。
『鬼滅の刃』のように、
- 死を悼む
- 生きた証が受け継がれる
- 未来に希望がある
といった構造は、まさにグリーフケアの視点からも有効な「心の処方箋」なのです。
まとめ:人は“死”の先に希望を求めている
『鬼滅の刃』が伝えてくれたのは、「死」は終わりではなく、「想い」は未来につながるということ。
この時代に、死を真正面から描き、それでも人が前を向いて歩めるような物語が求められているのは、決して偶然ではありません。
あなたの大切な人の“生きた証”も、誰かの心にきっと残り、次の世代へと受け継がれていくでしょう。
関連記事はこちら
- 【専門士が解説】「転生モノ」が流行る理由──現代人が“やり直し”を求めるわけ
- 【グリーフケアとアニメ】“死”をテーマにした作品が与える癒しの力とは
- 【終末期の現場から】人が死ぬということを、子どもにどう伝えるか?
この記事が、誰かの心の癒しになれば幸いです。