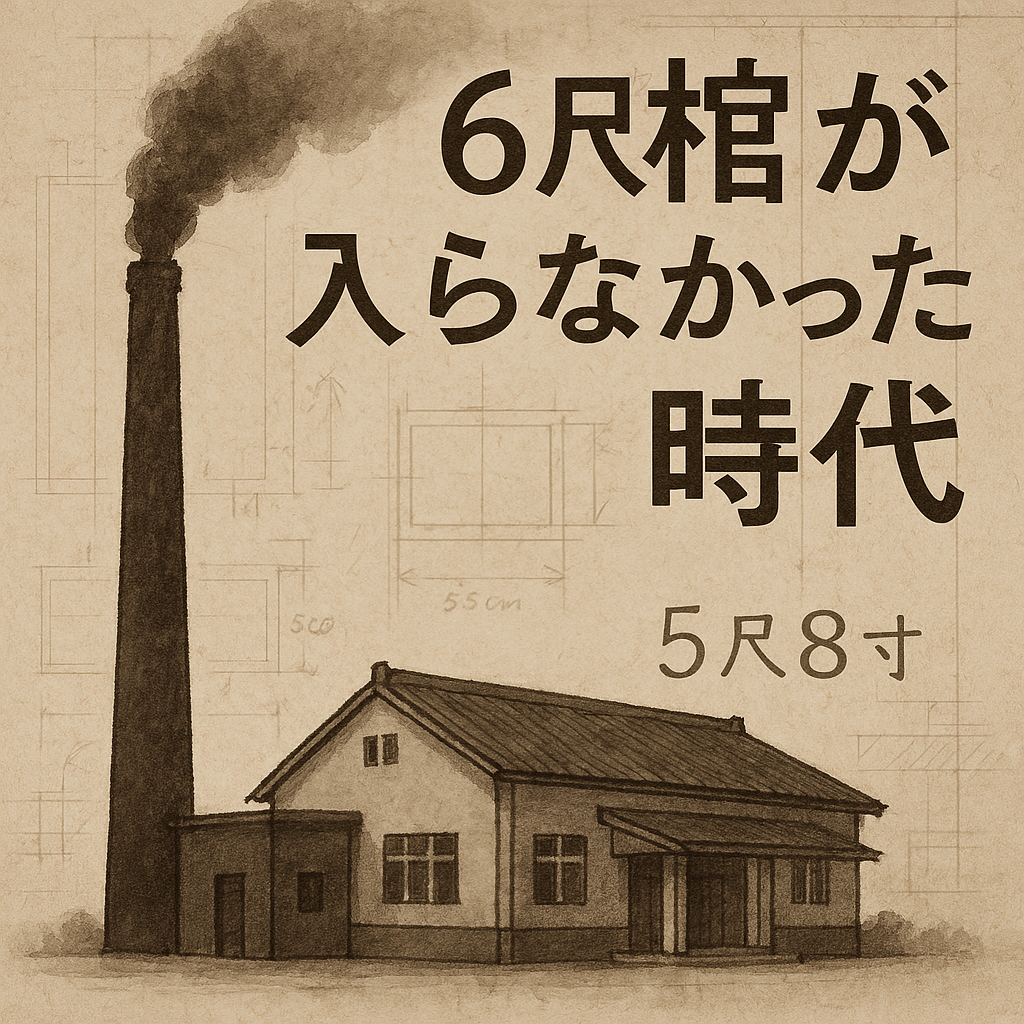2023.07.28 終焉の歴史を紐解く
【火葬vs土葬】実はまだ選べる!? 日本の火葬文化とその歴史をまるっと解説!

こんにちは、遺体修復士のエンゼル佐藤です。
本日は、日本人の葬送文化に深く関わる「火葬」と「土葬」について、歴史や法律の観点から分かりやすく解説していきます。
現代日本の火葬率は99%!でも土葬は「禁止されていない」
今では「亡くなったら火葬」が当たり前のように思えますが、実は土葬も法律で禁止されていません。
私は2022年に地元市役所の市民課に問い合わせたところ、条件はかなり厳しいものの、土葬許可証の発行は可能との回答をいただきました。
実は私の義祖母(夫の祖母)も、今から約30年前に土葬で埋葬されたんですよ。
火葬文化の始まりは江戸時代前期から
火葬が一般的になったのは、17世紀ごろ(江戸時代前期)とされています。
それまでは日本でも土葬が主流でしたが、火葬が広がった理由は大きく2つあります。
① 仏教の教えによる影響
仏教では、「亡骸を焼くことで魂が浄化され、次の世界へ旅立てる」とされています。
来世へ行くにはこの世の物を一切持っていけないという教えのもと、「無」になる=火葬という考え方が広まりました。
② 感染症対策の必要性
当時、疫病(熱病や風邪、インフルエンザのような病)が広まり、遺体が感染源になるのではないかという考えが生まれました。
火葬には「病原菌を封じ込める」という防疫的な意味もあり、公衆衛生の観点からも火葬が支持されていったのです。
なぜ仏教が広まったのか?17世紀の日本社会と宗教
江戸時代初期、日本は戦乱を終えたばかりで、政治や社会が安定しきっていない状況でした。
そんな時代背景の中で、人々は精神的な拠り所として仏教に救いを求めたのです。
その結果、仏教の儀式や教えが民間に深く根付き、火葬の文化も広がっていきました。
真言宗ってなに? 弘法大師(空海)の教えとは
仏教の中でも「真言宗」は特に厳しい修行が特徴です。
この宗派を広めたのが、あの有名な弘法大師(空海)です。
- 奈良時代末(774年)、現在の香川県に誕生
- 中国から密教を学び、真言宗を日本に広める
- 「即身成仏(この世で仏になる)」の教えを説く
- 晩年、高野山の奥の院で即身仏となり祀られる
真言宗では「三密(身・口・意)」を整えることが修行の基本とされ、行動・言葉・心の一致が求められる厳しい教えです。
宗教目的以外でミイラになった日本人がいた!?
仏教の即身仏とは別に、なんと宗教とは関係なく自分の意思でミイラになった日本人がいるんです!
江戸時代の本草学者(現在で言う薬学者)である彼は、生前にこんなことを考えていました。
「自分の体を保存して後世に見せたい」
彼はミイラ化のために、防腐作用のある「柿の種(タンニン)」を大量に摂取。
戦後、墓地移転に伴い発掘された遺体をCTスキャンで調べたところ、
脳は縮んでいたものの保存状態は良好でミイラ化に成功していました!
ミイラの皮膚が赤茶けていたのは、柿の種に含まれるタンニンの効果とされています。
彼の遺体は現在、上野・国立科学博物館の特別展「ミイラ展」で展示されています。
まとめ|火葬文化は宗教と感染症のダブル要因で広がった
火葬は「仏教的な思想」と「感染症対策」という2つの要因で、日本に定着していきました。
現代では常識となった火葬ですが、歴史を振り返ると時代のニーズに応じて変化してきた文化であることがよくわかります。
そして土葬も、完全に消えたわけではありません。
条件さえ整えば今でも土葬は可能なのです。
「火葬と土葬」――どちらが正しい、ではなく、それぞれに込められた歴史や信仰、社会背景を知ることが大切なのかもしれませんね。
今後も、葬送文化や遺体管理の現場から、役立つ知識やちょっとディープな雑学をお届けしていきます!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。