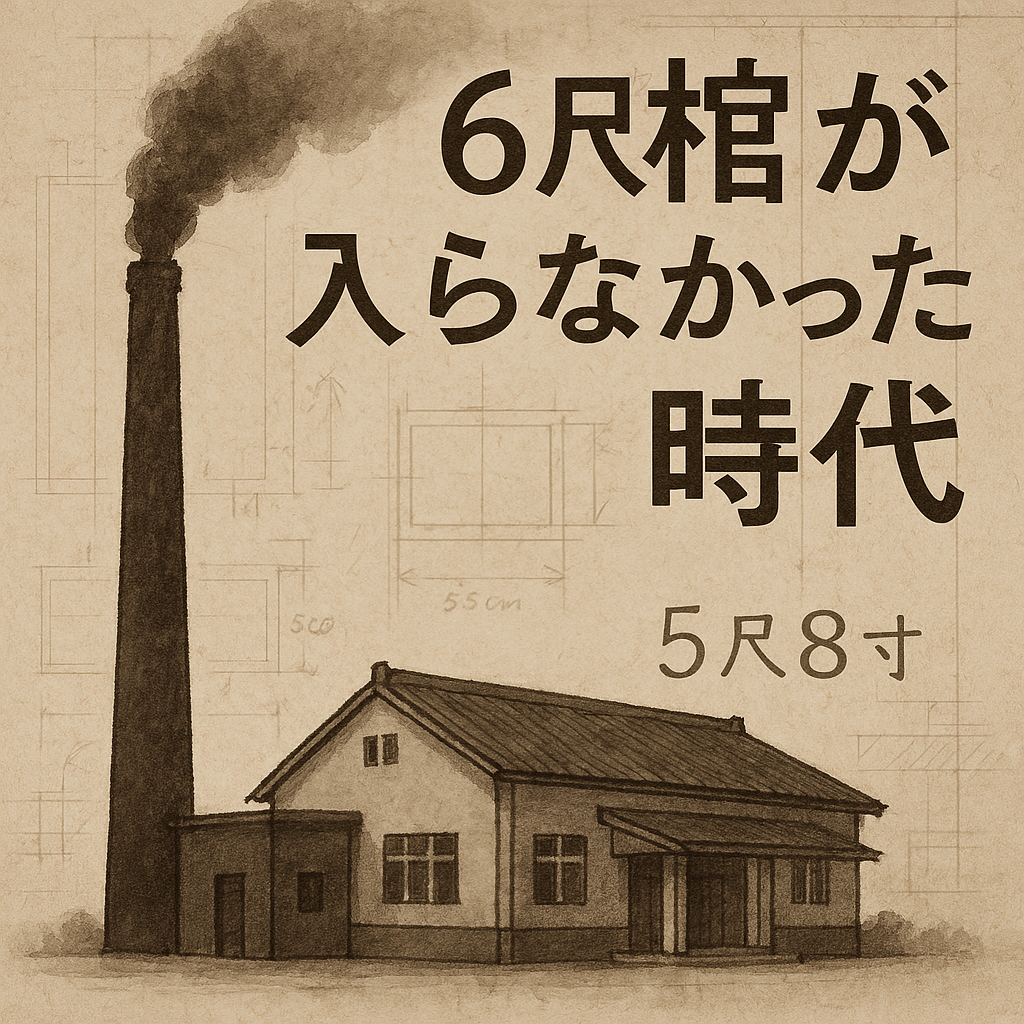2023.08.8 終焉の歴史を紐解く
【考察】仙台四郎のお墓はどこにある?行旅死亡人取扱法から読み解く“商売の神様”の最期

こんにちは、遺体修復士のエンゼル佐藤です。今回は「仙台四郎さん」の知られざるお話を、法的な視点から考察してみたいと思います。
東北、特に宮城県を訪れた方なら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
笑顔の男性が描かれた置物やポスター──そう、それが仙台四郎さんです。
実はこの方、江戸時代末期から明治時代にかけて実在した人物で、立ち寄ったお店が繁盛したという逸話から、「商売繁盛の神様」として現在も広く信仰されています。
ですが一つ、不思議なことがあるのです。
「仙台四郎さんのお墓がどこにも見当たらない」という事実。
今回はその謎に、かつて火葬場管理と行旅人処理に関わった私の視点から、「行旅死亡人取扱法」に基づいて迫ってみたいと思います。
仙台四郎とは? 笑顔と縁起を呼ぶ「福の神」
まず簡単に、仙台四郎さんについてご紹介します。
詳しくはWikipediaにも記載がありますが、要点は以下の通りです:
- 仙台生まれ(1840年頃)、1903年(明治36年)に48歳で死去
- 知的障害があったが、温厚な性格と笑顔で人々に愛された
- 放浪癖があり、列車で遠方まで出かけることも多かった
- 立ち寄った店がことごとく繁盛したため、「福の神」として知られるように
▶ 詳細はこちら:Wikipedia – 仙台四郎
仙台四郎さんのお墓が「存在しない」って本当?
不思議なことに、仙台四郎さんの墓所は現在も特定されていません。
彼の死は1903年(明治36年)で、福島県須賀川市で亡くなったと記録されています。
一説には「仙台駅前に墓があったが都市開発で埋められた」などの噂もありますが、公共事業での墓地移転ならば、きちんと改葬されるはず。
それなのに、「墓の所在が分からない」というのはなぜでしょうか?
ヒントは「行旅死亡人取扱法」にある
ここで関係してくるのが、明治32年に制定された「行旅死亡人取扱法」です。
この法律は、次のような人を対象としています:
行旅人(こうりょにん)とは:
旅行中・放浪中など、身元不明で所持金もなく、保護が必要な状態にある人
そして、こうした行旅人が死亡した場合、その処置や火葬費用は発見地の自治体が負担し、記録を残すことが義務付けられています。
📜 法律の詳細はこちら:
行旅病人及行旅死亡人取扱法(e-Gov)
仙台四郎は「行旅死亡人」だった可能性が高い
四郎さんは生前、各地を放浪し、無賃で列車に乗ったり、飲食をしたという逸話があります。
しかし実は、後から家族がすべての費用を支払っていたことも判明しており、家族に深く愛されていた存在だったことが分かります。
死亡地である福島県須賀川市で倒れた後、身元不明として「行旅死亡人」として処理された可能性が高いと考えられます。
そしてそのまま、簡素な火葬と埋葬が行われ、無縁仏としてどこかの地にひっそりと眠っている──
私は、そんな可能性に思い至りました。
明治時代の背景にある「行旅人の悲劇」
この法律ができた背景には、非常に悲しい事情があります。
明治以前、貧しい家庭では「死にかけた家族を旅支度させて家から追い出す」風習があったといいます。
行き倒れとなってどこかで亡くなり、無縁仏として葬られる人々──それを救済するために作られたのが「行旅死亡人取扱法」なのです。
今の私たちからすると胸が痛む話ですが、その時代にあっても、家族の手を離れて自由に旅をし、笑顔で人々に福をもたらした仙台四郎さんは、とても幸せな存在だったのかもしれません。
まとめ:お墓がなくても、仙台四郎は今も「心の中」に生きている
お墓は見つからなくとも、仙台四郎さんの笑顔と福をもたらす伝説は、今も多くの人に受け継がれています。
商売繁盛の神様として、あちこちのお店に祀られる存在。
そして、行旅死亡人としての最期にそっと寄り添う、明治の日本の優しさ──
私たちがその歴史に目を向けることも、供養のひとつなのかもしれません。
🔍 関連キーワード:
仙台四郎 お墓 どこ 行旅死亡人取扱法 無縁仏 福の神 放浪 須賀川 火葬場 明治時代の法律
ご感想やご質問があれば、ぜひコメント欄からお寄せくださいね。
次回も、知られざる「遺体と法律の世界」から興味深い話題をお届けします。