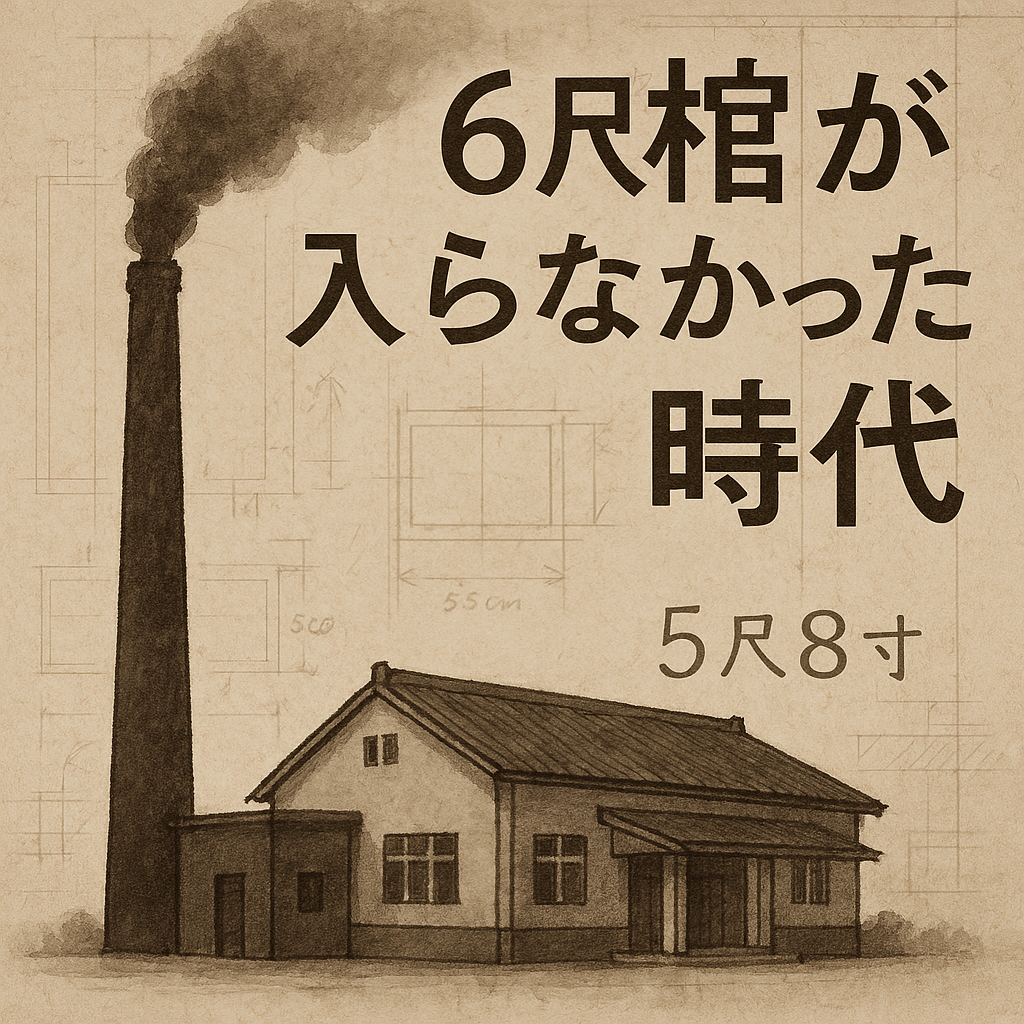2022.01.28 終焉の歴史を紐解く
死後の車窓から

【天に喰われる死体!?】チベットの“鳥葬”と日本人が忘れかけた死後の物語
こんにちは、遺体修復士のエンゼル佐藤です。
今回のテーマは、ちょっと怖くて、ちょっと切なくて、だけど超面白い——“死後の遺体はどう扱われるのか?”について。
タイトル、見覚えありますよね?
そう、某テレビ局で1987年から放送されている超・超・長寿紀行番組「世界の車窓から」のオマージュ……と思いきや、今日はもっと深〜い、そしてディープでダークな“死後の車窓から”をお届けします。
■世界の果てで、死体は天に喰われる——チベットの鳥葬とは?
あなたは“鳥葬(ちょうそう)”をご存じでしょうか?
それは、亡骸をハゲタカに食べさせるという、現代日本では絶対に地上波放送できない衝撃の葬送方法。
かつて私が子ども時代に観た「素晴らしい世界旅行」という日立のドキュメンタリー番組で初めて知り、あまりのインパクトに魂が震えたのを覚えています。
チベットでは、亡骸は「ただの器(うつわ)」であり、魂はすでに天に還っているという考え方があるのです。
だからこそ、躊躇なくその器を鳥たちに捧げる。そう、それは“天葬(てんそう)”とも呼ばれています。
なんというスケール感!
なんという死生観!
怖い……けど、美しい。
■鳥葬だけじゃない!チベットのカオスな葬送文化
チベットの葬儀には鳥葬の他にも、
- 土葬(伝染病や犯罪者など)
- 水葬(乳幼児や貧しい人)
- 火葬(高名な僧や貴族・学者)
- 塔葬(ダライ・ラマ級の聖人)
「死」とは、魂のグラデーションであり、生前の徳や社会的地位で“送り方”が変わる——まさに人間の最期を表現するアートなのです。
ちなみに、チベットは標高が高く木が少ないので薪が貴重。
冬は土が凍るため、土葬も困難。そんな地理的背景もあって鳥葬が最も一般的に。
四川省のラルンガルゴンパという僧院では、なんと観光客向けに鳥葬を公開していた時期もありました(2006年以降は撮影禁止)。
気になる方は「Tibetan Sky Burial」「Bird Cremation」で検索してみてください。ヒヤッとする映像が見つかるかも……。
■エジプトのミイラは“魂の帰還”のためにあった?
一方、魂が“器”に戻ってくると信じたのが古代エジプト人。
だからこそ、遺体をミイラにして完全保存。ピラミッドはただのお墓じゃなく、“魂を復活させる装置”だったという説も。
ミイラ vs ハゲタカ。
保存 vs 還元。
この対比、ゾクゾクしませんか?
■日本人の死生観も変わりつつある?
かつては「お墓がなければ死ねない!」くらいの勢いだった日本人ですが、最近では
- 墓じまい
- 海洋散骨
- 永代供養墓
- 樹木葬
など、「お墓を持たない選択肢」が急増中。
もしかすると、我々も“魂は器に宿る”という感覚から、“魂は自由”という考え方にシフトしてきているのかもしれません。
■まとめ:あなたの魂は、どこへ行きますか?
死は終わりではなく、文化の鏡。
鳥葬、ミイラ、お墓じまい……それぞれの葬送には、その土地の哲学と死生観が込められています。
あなたは自分の“器”をどう扱ってほしいですか?
——天に喰われるか、未来に蘇るか。
それとも、静かに海に溶けていくか。
死後の旅路は、まだまだ奥が深いのです。
もし気に入っていただけたら、「いいね」や「シェア」で応援していただけると嬉しいです!
次回は「火葬の起源とゾロアスター教の“風葬”」についても書こうかと企み中……。