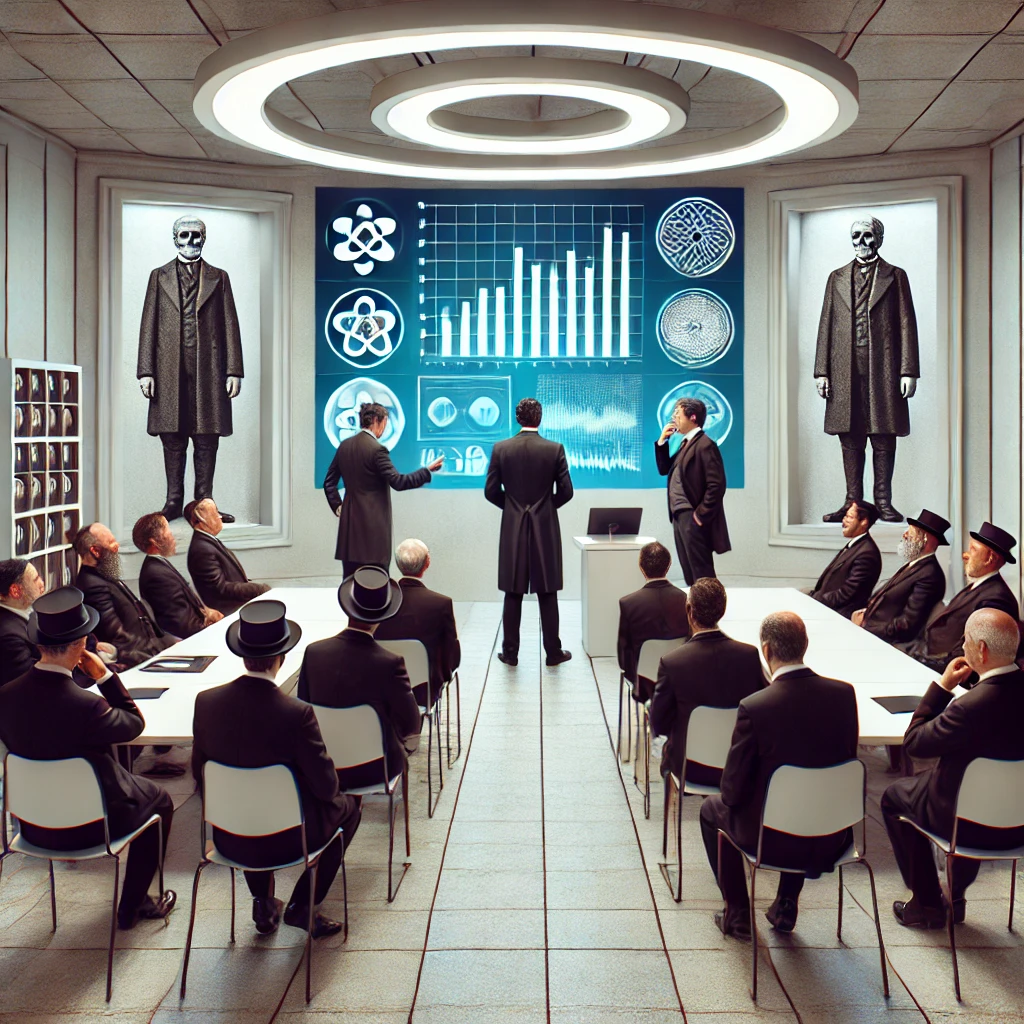2025.03.23 エンゼルケアにおける事例
【シリーズ第3弾】冷えていないご遺体葬儀社が学ばない「遺体冷却の科学」と現場で進む誤った常識

葬儀業界では、ご遺体を清潔に保ち、美しい状態でお別れに臨めるようにすることが基本とされています。
しかし、科学的に適切な「遺体の冷却」について、正しい知識を持たずに業務を行っているケースが、いまだに多く存在しているのが現実です。
これは感染リスクや腐敗進行、ご遺族の精神的ケアにも大きく関わる問題です。
法医学的に正しい「遺体冷却」の定義とは?
遺体の腐敗を抑えるには、死後6時間以内に深部体温(体腔内温)を5℃以下に下げる必要があるというのが法医学的な見解です。
この「6時間以内・深部5℃以下」の目標は、細菌の増殖を抑え、腐敗を遅らせるために最も効果的な冷却条件とされています。
冷却に必要なドライアイスの適正量と部位
葬儀の現場では、ドライアイスが冷却に用いられます。しかし重要なのは、使用量と配置部位です。
- 適正量:ご遺体の体重の約20〜30%(例:50kgの方なら10〜15kg)
- 冷却部位:腐敗が始まりやすい腹部を中心に配置
これは、腐敗が主に脳と腹腔内の内臓から進行するという科学的根拠に基づいています。
実際の現場で横行する「間違った冷却」
ところが現場では、ドライアイスを一律10kgと決めて使用している葬儀社が多数存在します。体重や保存時間、気温などに関係なく、この「10kg固定」がルール化されている例も珍しくありません。
さらに、「頸動脈を冷やすと全身が冷える」という医学的根拠のない迷信が、現場では今も信じられているのです。
保冷剤(エコパック)による冷却は不十分
コストを削減する目的で、「エコパック」と呼ばれる保冷剤で冷却を済ませてしまうケースも増えています。
しかし保冷剤は、凍結温度が高く冷却持続時間も短いため、体腔内部まで温度を下げることができません。 これでは、表面温度は下がっても、内臓からの腐敗は防げません。
なぜ、誤った冷却方法が続くのか?
ここでも「ゼンメルベイス反射(Semmelweis Reflex)」が作用しています。
ゼンメルベイス反射とは、新しい正しい知識が、従来の慣習や多数派の価値観に反することで拒絶されてしまう心理現象です。
例:
- 「昔から10キロでやってるから大丈夫」
- 「頸を冷やせば充分と習った」
- 「保冷剤の方が見た目が良いから安心」
こうした言説は、科学的根拠ではなく“思い込み”や“コスト優先”で現場の判断がなされている証拠です。
故人への敬意は「腐らせないこと」から始まる
腐敗が進めば、体液漏出・異臭・ご遺族の心理的ダメージにもつながります。これは火葬されてしまえば見えなくなるものではありません。
冷却管理とは、単なる保存技術ではなく、ご遺体への敬意とご遺族への思いやりを具体的に示す行為です。
「腐るのが当たり前」ではなく、「腐らせない努力」がプロの責任なのです。
次回予告(シリーズ第4弾)
「仏さんは頸動脈を冷やす」?
――葬儀業界に残る“笑えない迷信”と科学的視点からの検証
関連キーワード:
遺体冷却 ドライアイス量 / ご遺体 腐敗防止 / 頸部冷却の誤解 / エコパック 冷却効果 / 法医学 遺体温度管理 / ゼンメルベイス反射 葬儀業界