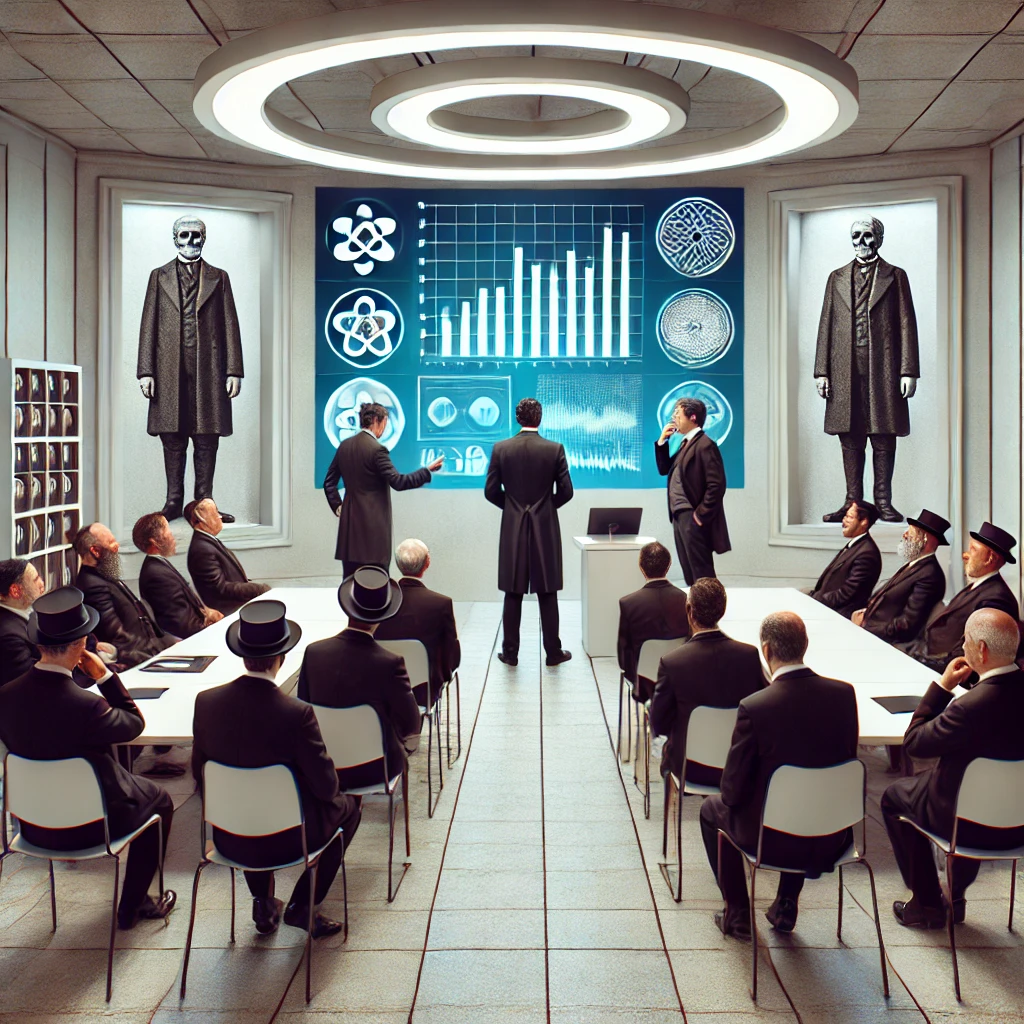2025.03.23 エンゼルケアにおける事例
予防していたのに──訪問入浴介助でB型肝炎に感染した私の体験

こんにちは。今回は、私が訪問入浴介助の現場でB型肝炎に感染してしまった実体験をお話ししたいと思います。
この出来事はもう20年以上前のことですが、「感染症対策の大切さ」や「介護現場の制度的課題」を深く考えるきっかけとなりました。
当時の現場では、感染症の情報は共有されていなかった
1991年から2000年まで、私は地方自治体が運営する訪問入浴介助サービスに従事していました。
手洗いやグローブの着用といった基本的な感染症対策は行っていたものの、利用者の感染症の有無は事前に共有されず、リスクを抱えたまま日々の介助を行っていました。
それでも「自分は大丈夫」と思っていた
「自分は手洗いもしてるし、予防もしてるから大丈夫」──当時の私はそう思い込んでいました。
しかし、ある日体調の異変を感じて検査を受けたところ、B型肝炎ウイルスに感染していることが判明。
幸いにもキャリア化せず抗体ができて回復しましたが、あの時の恐怖は今も忘れられません。
介護保険制度が始まり、業務は民間委託に
その後、介護保険制度の開始により、訪問入浴サービスは民間事業者へと移行。私は事務方へ異動となりました。
しかし、現場では新たな課題が浮き彫りになっていきます。
予算不足でグローブすら使えない現場も…
介護現場は人手不足と慢性的な低賃金が課題です。さらに、予算の都合からグローブなどの衛生資材が十分に支給されない事業者も存在しました。
感染症に対する知識が乏しい管理者のもとで、感染リスクを軽視した運用がされているケースも見受けられ、コンプライアンスの観点からも大きな問題だと感じました。
地元事業者も撤退…背景にはコストと人材問題
私の暮らす市町村では、個人病院や農協が訪問入浴サービスに参入したものの、いずれも数年で撤退。
採算が取れないことや、スタッフの健康管理への不安もその背景にあったと思われます。
感染症対策は「個人の努力」だけでは防げない
この体験から強く実感したのは、どれだけ自分が注意しても、制度や現場の環境が整っていなければ感染症は防げないという現実です。
感染症対策は現場任せではなく、事業者・行政・社会全体の責任として捉えるべきだと思います。
最後に:介護の現場を「安心して働ける場所」に
感染症対策にかかるコストは、無駄ではなく「未来への投資」です。
人の命と健康を支える仕事に携わる人たちが、まず安全に守られること──それが本当に大切なことではないでしょうか。
この記事が、現場で働く皆さんや、介護・医療業界に関心のある方々にとって、何かの気づきになれば幸いです。
この記事は、現場経験と感染管理の資格を持つ「エンゼル佐藤」が執筆しました。介護・終末期ケア・遺体衛生管理などに関心のある方は、他の記事もぜひご覧ください。