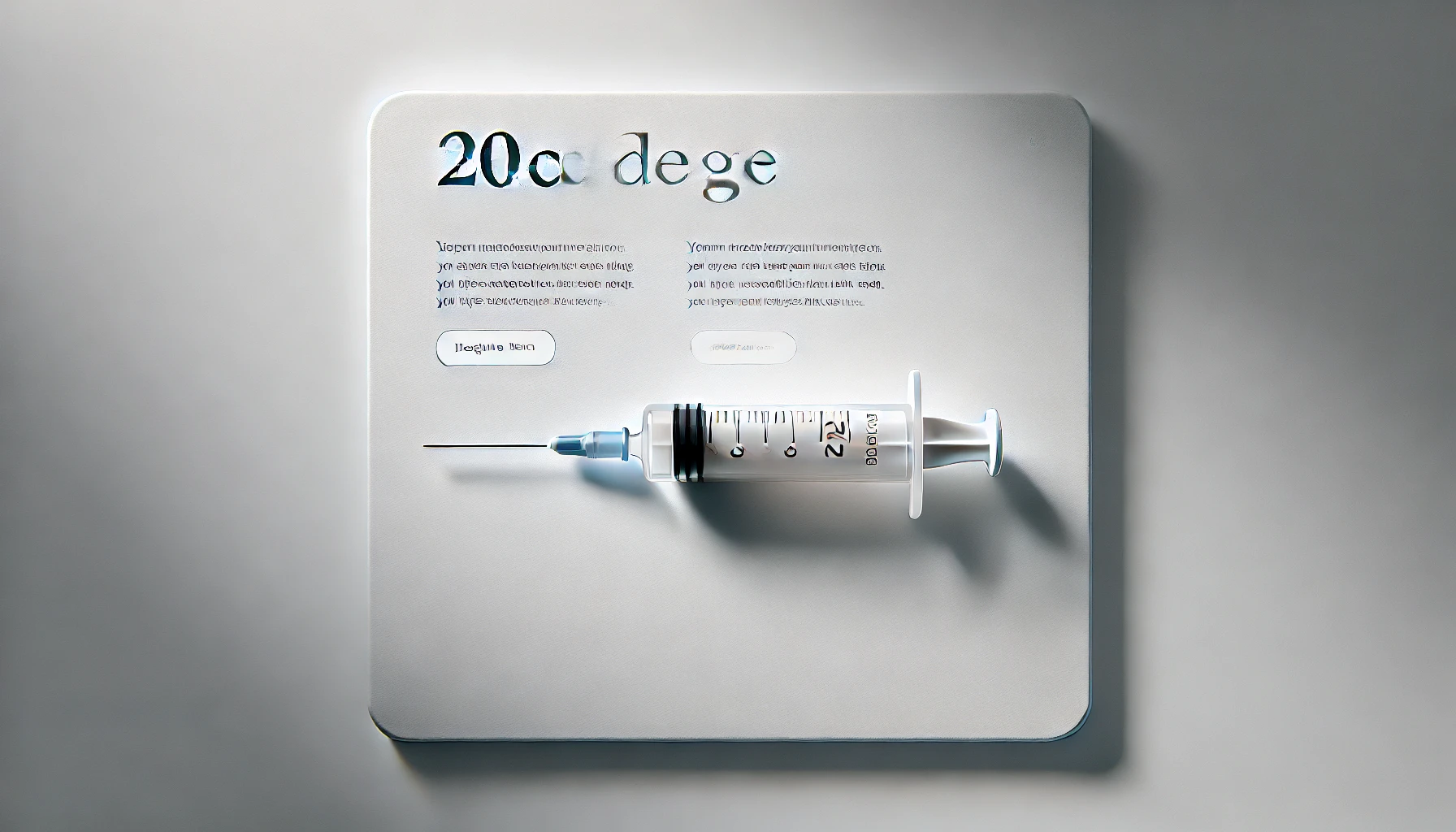2025.03.23 エンゼルケアにおける事例
納棺師という職業の実像を、法医学・感染症管理の視点から検証する

映画『おくりびと』(2008年)の大ヒットをきっかけに、日本社会に広く知られるようになった「納棺師」という職業。作品の印象的な所作や美しい描写から、多くの方が「納棺師」という存在に特別な意味や神聖さを感じるようになりました。
しかし、法医学や感染症管理の専門的視点から見ると、この職業の成立過程や業務の実態には、検証が必要な点が多く存在します。本記事では、納棺師という仕事の背景や現状、そして感染対策の課題について解説します。
映画から生まれた職業、「納棺師」とは?
「納棺師」はもともと医療や法制度に組み込まれた専門職ではなく、映画『おくりびと』の公開によって生まれ、民間によって確立された新しい職業です。
映画の所作指導を担当した葬儀社が後に「おくりびとアカデミー」を設立し、納棺師の育成をスタート。独自のカリキュラムでは、主に故人の着せ替えや化粧といった儀式的ケアに重点が置かれており、医学的な知識や法的理解は重視されていません。
納棺師の衣服はスーツ。衛生管理の視点では大きな問題
現在、多くの納棺師がフォーマルなスーツ姿で業務にあたっているのは、映画の印象によるものとされています。しかしこのスタイルは、感染症対策の観点からはきわめて不適切です。
スーツは防水性や洗浄性に乏しく、血液や体液が染み込んだ場合の二次感染リスクが高まります。
一方、医療従事者、介護士、救急隊員などは日常的に次のような個人防護具(PPE)を着用して感染から身を守っています:
- 防水ガウン
- 手袋(グローブ)
- マスク(N95またはサージカル)
- アイガードまたはフェイスシールド
遺体には死後も感染力を保持するウイルスや細菌(B型肝炎、結核、HIVなど)が残る場合があるため、納棺業務も本来これに準ずるべきです。
実際に寄せられる現場の声:「素手での湯灌・メイク」に不安を感じる納棺スタッフたち
私の元には、納棺業務に携わった元スタッフから「素手で湯灌やメイクをしていいのか?」という相談が何度も寄せられています。
多くの現場では、PPEの使用は「大げさ」「見た目が悪い」とされ、“美しさ優先”の価値観によって感染対策が軽視されている現実があります。
ゼンメルベイス反射と業界の“思い込み”
ここで紹介したい心理現象が、「ゼンメルベイス反射」です。 これは、新しい正しい知識が、従来の慣習や多数派の価値観に反するという理由で拒絶される現象のことです。
納棺師の現場では、
- 「スーツが正式」
- 「所作の美しさが大切」
- 「今までこれで問題なかった」
といった“常識”が、科学的根拠よりも優先されてきました。
しかし、それによってスタッフが感染のリスクにさらされたり、ご遺族の悲しみに傷を重ねてしまうのであれば、その常識は再考されるべきです。
感染対策は「見た目」ではなく「科学」で行うもの
納棺は亡くなった方への最後のケアであり、ご遺族の心を支える大切なプロセスです。だからこそ、見た目の美しさや演出だけでなく、科学的・衛生的に正しい処置が求められる時代です。
これからの納棺師には、法医学・感染症・心理ケアを含む多角的な知識と倫理観が必要不可欠です。
関連キーワード:
納棺師 感染症対策 / 納棺 PPE 使用義務 / 遺体処置 衛生管理 / 納棺 素手のリスク / おくりびとの現実との違い / ゼンメルベイス反射 葬儀業界
この第一弾を起点に、次回以降も葬儀現場に潜む“なんとなく”や“思い込み”を検証していきます。 第2弾では、葬儀業界で起きた他の「ゼンメルベイス反射」の事例をご紹介予定です。どうぞお楽しみに。