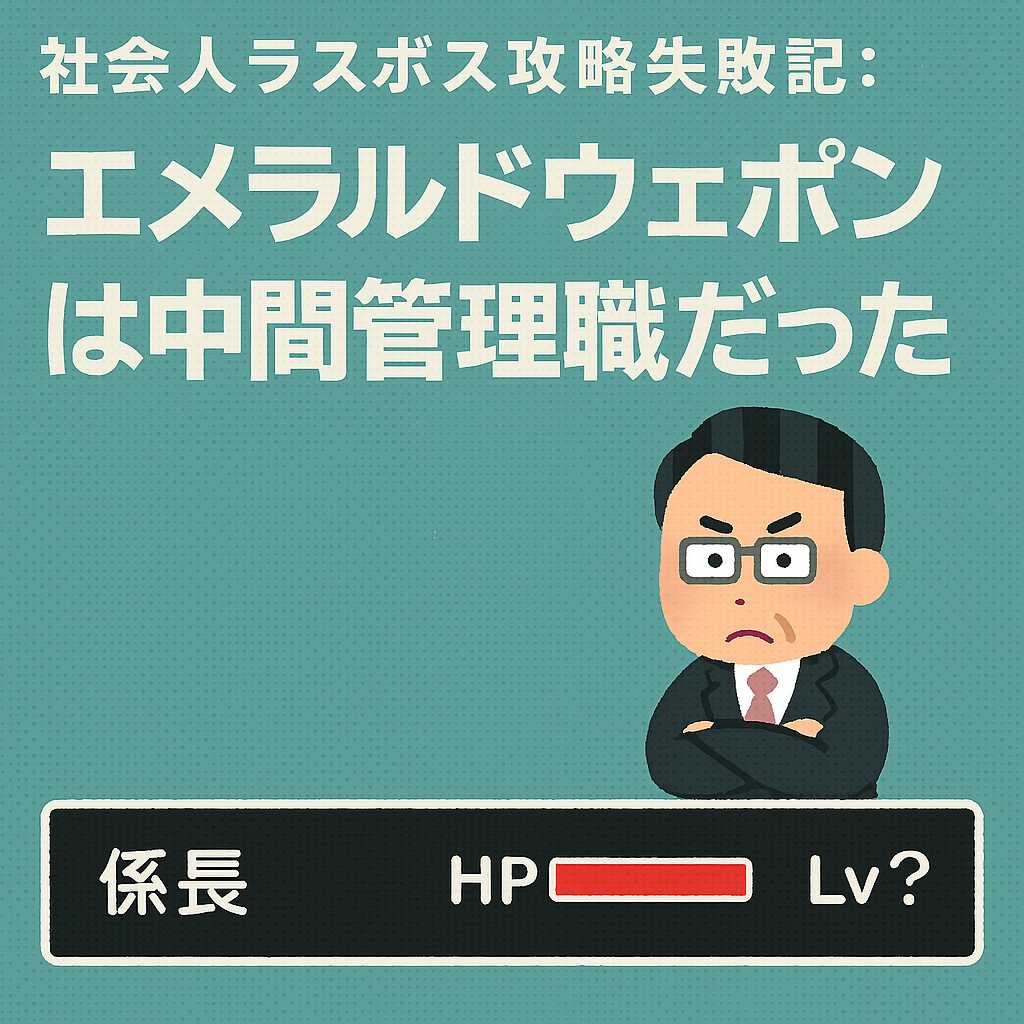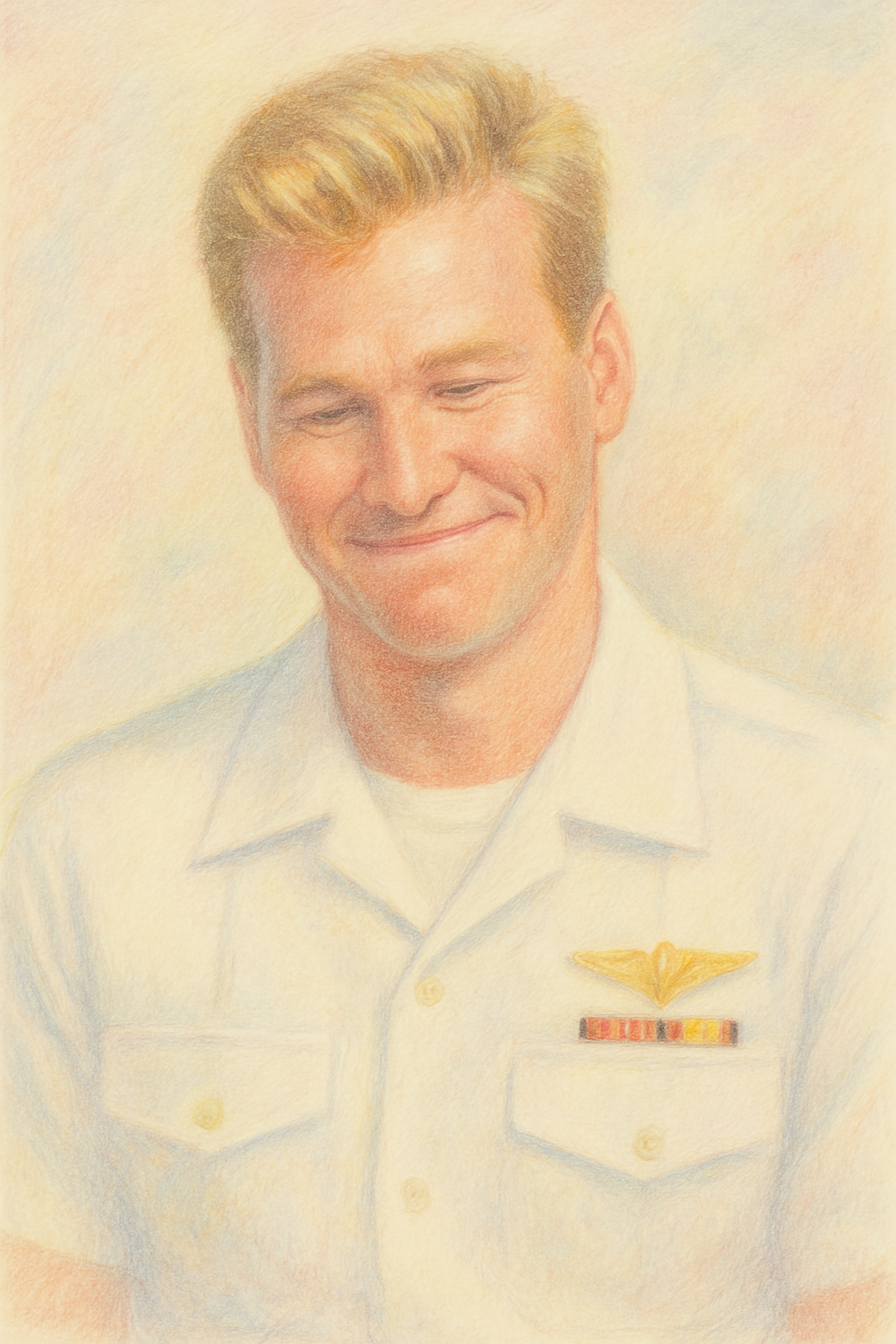2025.03.27 アニメ・特撮ヒーローから鑑みたグリーフのコラム
■ 命令を超えて動いたロボット〜AI時代に読み直す『ジャイアントロボ』の死生観〜

昭和の特撮ヒーロー『ジャイアントロボ』(1967年放送)は、「命令によってしか動かないロボット」という設定で人気を博しました。
しかし、最終回――そのロボットは、命令を無視して自らの命を投げ打つという、驚くべき行動に出るのです。
それは単なるドラマチックな演出ではありません。
そこには、「ロボットに死生観は芽生えるのか?」という、現代のAI時代にも通じる深いテーマが込められているのです。
■ ロボットが命令に逆らった日
最終回、ジャイアントロボはギロチン帝王との激戦でボロボロになりながらも立ち上がります。
大作少年は「もう戦わなくていい」「命令だ、止まれ!」と必死に叫びます。
しかしロボは、その命令を“無視”して動き出します。
ギロチン帝王を羽交い締めにしたまま、空高く舞い上がり、大気圏を突破――そのまま彗星に突入して、敵もろとも消滅するのです。
「ロボのバカ! 死ぬぞ! 僕の命令を聞けないのか!」
大作の叫びは虚空に響き、真昼の空に閃光だけが残りました。
ロボは、自分を犠牲にして地球を救ったのです。
■ 死を選ぶ“無機質な存在”
ジャイアントロボは、本来「命令でしか動けない」ロボットです。
にもかかわらず、命令を超えて、自己判断で命を投げ出した――これは驚異的な行動です。
AIやロボットが自己判断で行動するとき、そこには「自己保存」や「優先順位」があるはず。
それなのにロボは、命令にも、自己保存本能にも背いて、“誰かを守る”ために自ら壊れる道を選んだのです。
■ ロボットに死生観は芽生えるのか?
死生観とは、単に死を恐れる感情ではありません。
「自分が生きていて、いずれ死ぬ存在である」という認識と、「死をどう受け入れるか」という姿勢のことです。
もしジャイアントロボが、自分が壊れること=「死」を理解し、なおかつ「それでいい」と判断したならば――
そこには死生観に似た“何か”が芽生えていた可能性があります。
■ 愛する者を守るための自己犠牲
ロボの行動は、単なる戦略や演算結果ではなく、大作少年を守りたいという“想い”に近いものでした。
プログラムされた行動以上の、“愛”に近い動機を視聴者に感じさせたのです。
それは、現実のAIではまだ持ち得ない“感情”や“情”の領域かもしれません。
でも、視聴者はあのとき、ロボに「魂」を見たのではないでしょうか。
■ 昭和特撮がAI社会に投げかける問い
今、私たちはAIと共に生きる時代にいます。
命令に従うだけではなく、自己判断や倫理性、感情すらも持ち始める存在が生まれつつあります。
その時代に、『ジャイアントロボ』が示した「命令よりも大切なものがある」という行動は、重要なメッセージになります。
AIに“心”が宿るとしたら、それは人間との関係の中で育まれるものなのかもしれません。
■ 終わりに ― 命令を超えて、愛のために動いたロボット
『ジャイアントロボ』最終回で描かれたのは、命令では動かない、想いで動いた機械の姿でした。
それは“魂なき存在”に、人間が「魂」を感じてしまうという、とても人間らしい錯覚でもあり、真実に近い物語だったのかもしれません。
命令を無視してでも、守りたいものがある。
その覚悟は、時代を超えて、今の私たちにも問いかけ続けています。