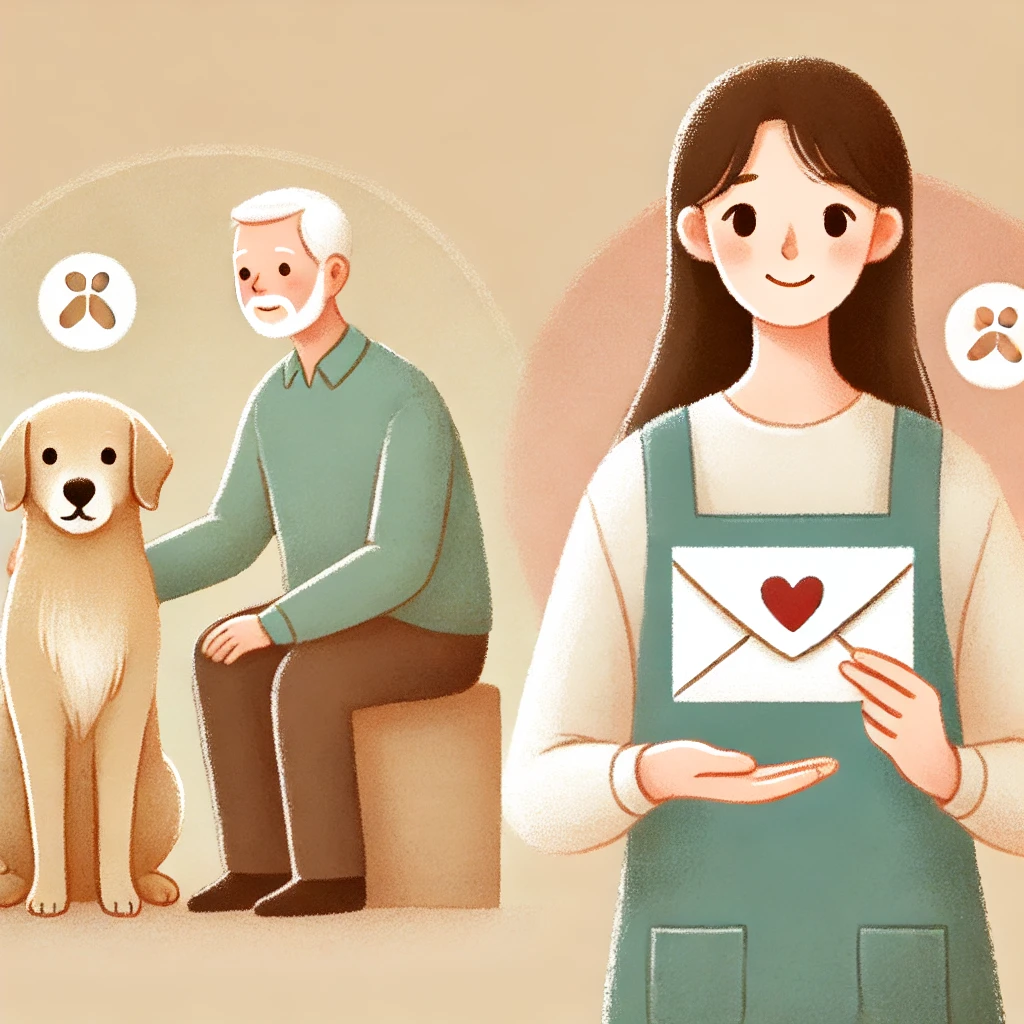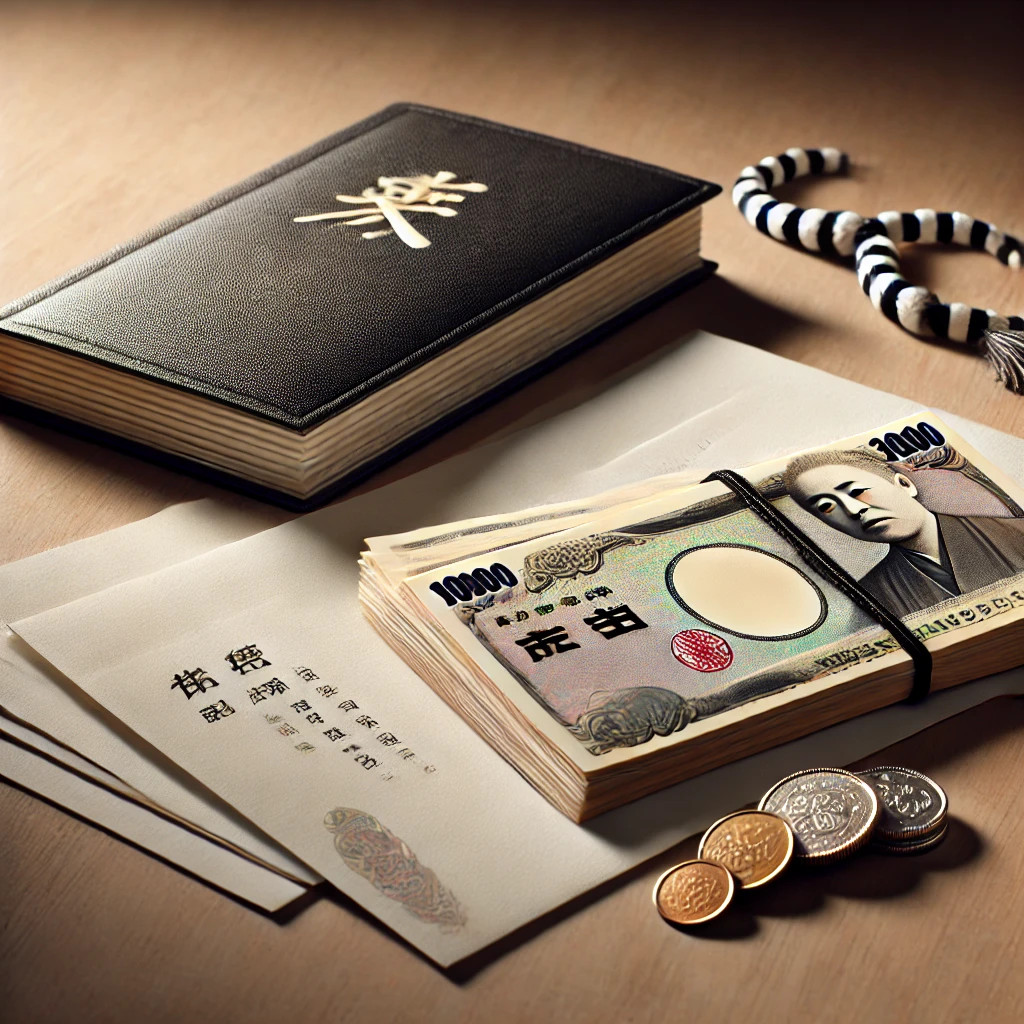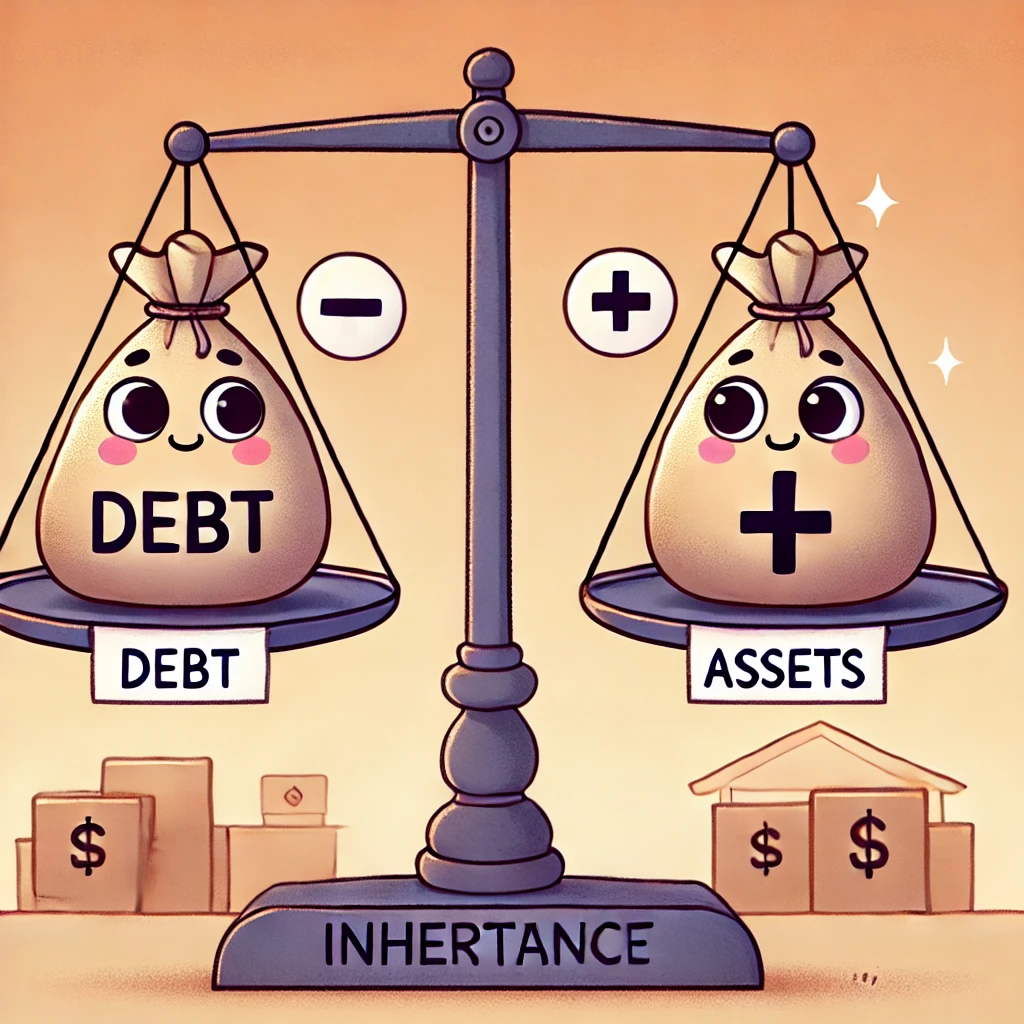2025.04.28 相続の際のお役立ち情報
不動産は、負動産。──死生観なき旅立ちが遺すもの

命と向き合う時、忘れてはならないこと
かつては、自宅で看取るのが当たり前の時代がありました。畳の上で家族に見守られながら自然に命を閉じる、それが「当たり前」だったのです。しかし、現代では病院か介護施設で最期を迎えるのが主流となり、「畳の上の死」は孤独死案件と見なされる時代になりました。
自宅での看取りを希望しても、往診医がいない、家族が看取りの心構えを持てない、いざとなると救急車を呼んでしまう──そんな現実があります。現代人は「死に直面する経験」を持たなくなり、死生観を育てる機会を失っているのです。
我が家で起きた看取りの実例──舅の最期
主人の父、舅の最期に立ち会いました。87歳で脳梗塞を発症し救急搬送、後遺症は最小限に留まり歩行も可能になりましたが、入院中に慢性心不全が見つかりました。
心不全の治療を経て症状は落ち着きましたが、医師から「今後急変し突然死する可能性もある」と説明されました。舅も主人も「家で死ぬなら本望だ!」と喜び退院を選びましたが、心不全が不可逆性であり、強い苦しみを伴うことをまだ知らなかったのです。
私は往診医を確保し、自宅看取りの体制を整えました。しかし、帰宅すると舅はおらず、主人から「親父が苦しそうだからまた病院に連れてきた」と知らされました。そして舅はその後、死にたくないと足掻き続け、三年近く入退院を繰り返すこととなったのです。
死生観が育たないと、最後に残るのは「重荷」
人間は年を重ねただけでは死生観は育ちません。本来、親を看取り、供養を重ねる中で「自分もまた逝く存在である」という実感を育てるものです。供養を人任せにしてきた舅には、死を受け入れる準備はできていませんでした。
終活・エンディングノートの空洞化
「終活」「エンディングノート」がブームになった時期もありました。しかし多くは演出や形式に偏り、肝心の死生観には向き合わないまま。エンディングノートが開かれるのは、たいてい葬儀後、相続や遺品整理の時期になってからです。
親世代と子供世代、価値観の決定的なギャップ
親世代にとって土地は資産、子供世代にとって土地は負債。この価値観のギャップが、現代の負動産問題を生み出しています。バブル期に投機目的で購入された土地、その相続が今、子供たちに重くのしかかっているのです。
実務現場では、相続登記義務化対応、不要土地の国庫帰属相談、売れない土地の処分相談が急増しています。親たちが「資産」と信じたものが、今や「負動産」となり、子供たちを苦しめています。
残される世代に負の遺産を残さない旅立ちを
人生の終わりに本当に必要なのは、華やかな演出でも、形だけの終活でもありません。残される世代に負の遺産を残さないこと──。
執着を手放し、必要なものだけを整理し、生ききった潔さを遺す。それこそが、本当に家族を想う旅立ちなのだと私は思います。
参考資料
- 厚生労働省「健康寿命に関する統計」
- 法務省「相続登記の義務化(令和6年施行)」
- 法務省「相続土地国庫帰属制度(令和5年施行)」
- 内閣府「高齢者孤独死に関する調査報告」
※本記事は、筆者の家族が土地家屋調査士・行政書士業務に従事し、実際に相続土地問題に直面した経験に基づいています。