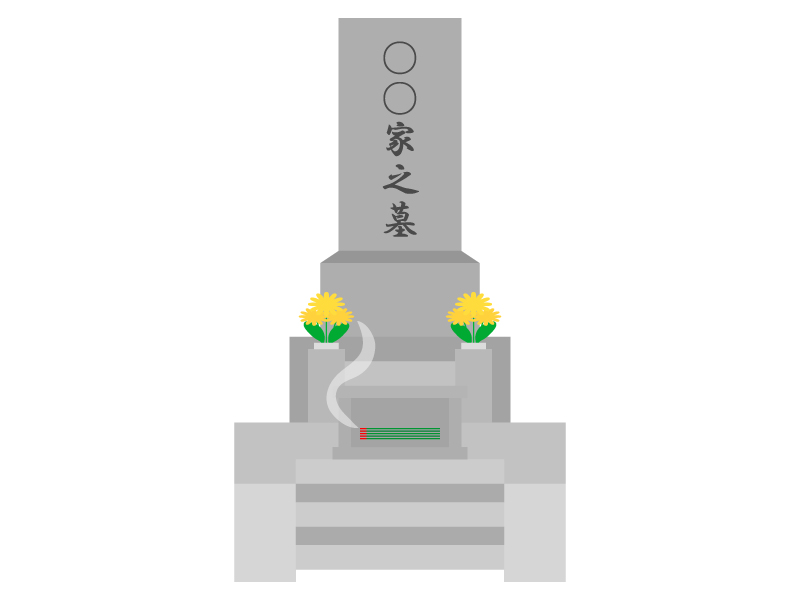2019.12.3 終焉の場での豆知識
【家族葬が当たり前?】そもそもお葬式って何だったの?〜昔の葬儀と現代を比べてみた〜

こんにちは。
遺体修復士のエンゼル佐藤です。
最近、「家族葬」がすっかり当たり前になってきましたね。
でも、そもそも「お葬式」って何のためにあるのでしょう?
今回は、自宅葬が主流だった頃の体験や、葬儀のルーツをたどりながら、現代の葬儀の姿をちょっと俯瞰してみたいと思います。
昔のお葬式は“ご近所総出の大イベント”
30年ほど前、私も婚家で「自宅葬」を経験しました。
当時はまだ「家で送る」のが当たり前。
ご近所さん(いわゆる“組内”)が集まって、自然と役割分担が始まります。
- 男性陣 → 墓穴を掘る、葬儀進行の相談
- 女性陣 → 台所に立って、せっせと料理
手順や段取りは、前回の葬儀を担当した家から「台帳(マニュアル)」を引き継いで、それを参考に進めていました。
そもそも、葬儀ってどう始まったの?
お葬式の起源はとてもシンプル。
誰かが亡くなったときに「家族だけじゃ手に負えないから、みんなで助け合って処理しよう」って始まったんです。
人が集まればお腹も空く。
自然と「じゃあご飯作ろう」→「そのうち決まったメニューになった」→「“お膳”が誕生」と進化していったんですね。
「葬儀」という“形”の誕生
こうして少しずつ、決めごとが生まれて、ルールが整っていった結果、「お葬式」という“形”ができました。
最初はリーダーシップのある人が進行を務め、やがて「この人、慣れてて上手いね」ということで進行役が固定化。
それがいつしか「葬儀屋さん」という職業になっていきました。
日本の葬儀の歴史をひもとくと…
日本の葬儀が今のように“お坊さん付き”になったのは、江戸時代以降。
- 1635年(寛永12年):寺請制度スタート。日本人全員がどこかのお寺の檀家に。
- 1700年(元禄13年):位牌・仏壇・戒名などの制度が整備。
それ以前は、村の共同体「葬式組」が葬儀を担っていました。
仏具や棺桶の制作は大工などの職人が兼任しており、これが“葬儀屋さん”の始まりとも言えます。
暮らしの変化とともに、葬儀も変わった
昔の農家は「人がたくさん集まること」を前提に家を建てていました。
大広間や普段使わない客間も、葬儀や法要を意識した設計でした。
でも現代の住宅にはそんな広い部屋は不要。
ライフスタイルの変化と共に、「家族だけで静かに」という葬儀スタイルが主流になったのも自然な流れなのかもしれません。
まとめ:お葬式とは“みんなで送る行為”だった
お葬式は、「手のかかることだから、みんなで協力して送ろう」という文化の結晶です。
現代のように業者にお願いするスタイルも便利ですが、その根底には“助け合い”の精神があったことを、忘れてはいけませんね。
【注意】「俺が死んだら、山に捨ててくれ」は犯罪です!
たまに、「俺が死んだら、す巻きにして山にでも捨ててくれ」という方がいますが…
それ、立派な犯罪(死体遺棄罪)です!
日本に“誰のものでもない土地”はありません。山だって、誰かの所有地です。
「煙のように消えてなくなりたい」なんて言っても、人は煙じゃないので消えません!
最後に…
葬儀のカタチは変わっても、人を想う気持ちはずっと変わらないもの。
自分や大切な人の「ちょうどいいお別れの形」、今のうちから考えておくのも大切かもしれませんね。